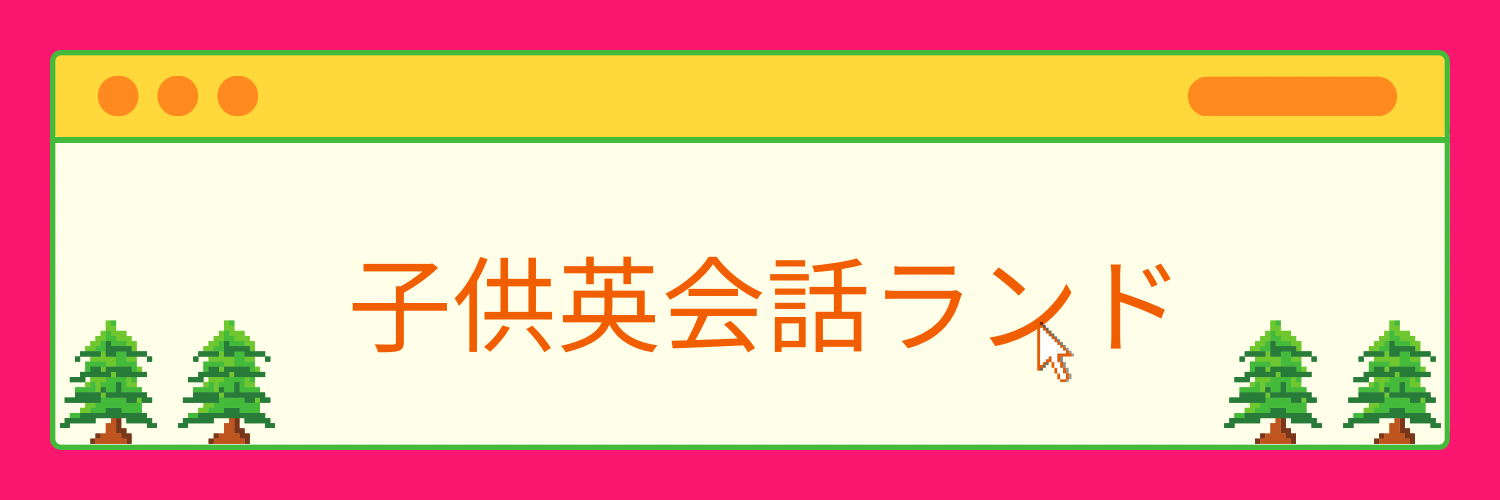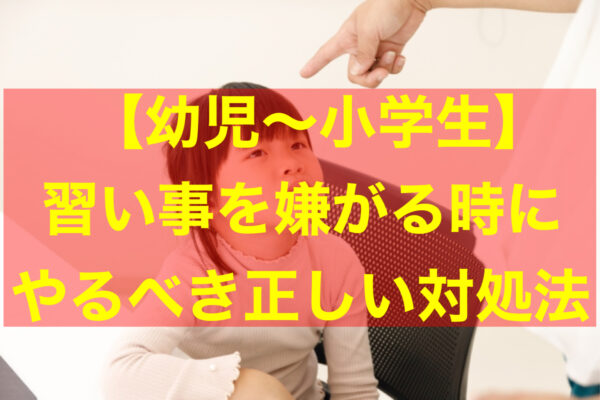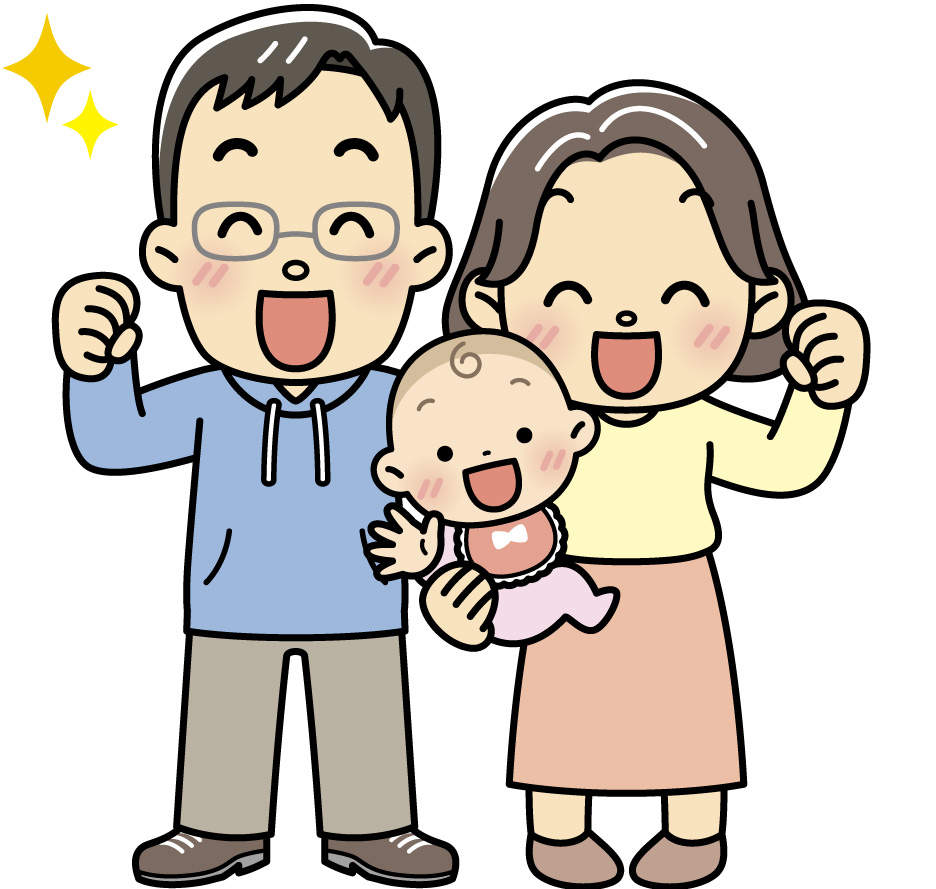子供が習い事を始めて、急に「習い事に行きたくない!」と言われたことありませんか?
一度は訪れる習い事のイヤイヤ期。
急に言われて困ってしまうこともありますよね。
嫌がる子供をみてイライラしてしまうこともあるかもしれません。
習い事に行きたくないと言われた時に
- 子どもが習い事を嫌がるときどうすればいいの?
- 正しい対処法って何?
- 怒っていいの?
- 無理やりでも連れていくべき…?
- もので釣ってみる?
- 辞めさせるべき?
など分からないことも多いのではないでしょうか?
今回は子供が習い事を「嫌がるときの正しい対処法」を解説していきます。
同時にやってはいけない事や体験談も紹介するので参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-

-
子供が英語を嫌がって勉強しない理由を徹底調査!その原因は親にもあった!?
「英語を学ばせたいけど、嫌がって何もできない…」 「ぜんぜん英語に興味をもってくれない」 「英語教室に行きたくないと駄々をこねる…」 グローバル時代が到来し、小学校での英語の教科化など、 ...
続きを見る
目次
子供が習い事を嫌がる時に
やってはいけない3つのルール

- 物で釣る
- 無理やり連れて行く
- 理由を聞かずに「じゃあ、辞めれば?」という
上記が子供が習い事を嫌がっているときに、やってはいけない対処法です。
順に解説します。
1.物で釣る
「物で釣る」は、その場しのぎで解決しません。
子供が習い事を嫌がっているときに、やってはいけない事1つ目は「もので釣る」ことです。
一度はやってしまおうと考えたことがある親御さんも多いのではないでしょうか?
もちろん、その場しのぎになる事はあります。
ですが、「我慢すれば○○を買ってもらえる..」とワガママになってしまう可能性があります。
例えば、
- 今日スイミング行ったら、帰りにお菓子買ってあげる!
- 英会話行ったら沢山ゲームやっていいよ!
- くもん行ったらYouTube見ていいよ!
このような誘いで一度は習い事に連れて行こうと考えることもあると思います。
ですが、物で釣って習い事に行っても何も解決しません。
そのような状態で習い事に行っても、習い事の効果を得ることは難しくなります。
2.無理やり連れて行く
「無理やり」連れていくと、次回はさらに嫌がる
無理やり習い事に連れて行っても教室でずっと泣いていて先生を困らせてしまったり、トラウマになってしまう子もいます。
- お母さんも忙しいんだから、わがまま言わないで!
- いいから早く行って!
- 習いたいって言って始めたんだから、ちゃんと行って!
習い事の数時間前に「急に行きたくない」と言われ時間がなく、無理やり連れて行ったことありませんか?
そんなときは、習い事の教室につくまでの通学時間に「嫌がる理由」を聞くようにしましょう。
現地についてもどうしても嫌ということであれば、習いごとの先生に謝罪をして休むことをおすすめします。
3.理由を聞かずに
「じゃあ、辞めれば?」という
「じゃあ、辞めれば?」は子どもにとってはキツい一言。
親としては月謝も払っているし、時間もとられるし、イライラしているときはつい「やりたくないなら辞めれば?」と言ってしまうこともあるかもしれません。
中には、本当に辞めることになるかもしれないと不安に思い、行こうとする子どももいるかもしれません。
ですが、この言葉を言うときは必ず「習い事に行きたくない理由を把握してから」にしましょう。
子どもが習い事を嫌がる時の対処法

- 子供が習い事を嫌がる、辞めたがる時には「嫌な理由」を聞き出そう。
- 叱る、言い聞かせるはNG!
では、順に説明します。
子供が習い事を嫌がる、辞めたがる時には
「嫌な理由」を聞き出そう
ただ単に面倒くさいのか、習い事そのものが嫌なのか、教室(先生や友達)に不満があるのかで親の対応も変わる。
未就学児の習い事の一部には、「保護者同伴、または見学可能」なものもありますが、習っている様子を見ることができない習い事も多いです。
ですので、教室でどんな様子か確認しにくい部分があります。
子供が嫌がる原因がどこにあるかで、それぞれ対応が変わってきますので、「嫌な理由」は子供に確認しておきましょう。
親の声かけ、励ましで乗り切れるケース
- 通塾、準備が面倒である
- ママ、パパから離れるのが嫌
先生と相談または、教室を変えるケース
- 宿題が多くて嫌
- 先生と合わない
- 他の生徒とトラブルがある
辞めてもOK(あるいは休会)のケース
- 習い事自体が嫌い
- 習い事がストレスになってしまっている
「嫌な理由」を確認することで、上記のように対応が変わりますので、しっかりと原因を探しましょう。
叱る、言い聞かせるはNG!
親の意見を押し付けるのは習い事を嫌いになる原因
子どものためを思って習わせた習い事を、子どもが嫌がる、辞めたがる時、どのように対処すればよいのでしょうか?
厳しく叱ったり、続けるよう言い聞かせてしまったりするママ・パパも多いと思います。
親から見ると「飽きっぽい」、「怠けたいだけ」などと感じるかもしれませんが、まずは嫌な理由を聞きましょう。
理由によって習い事を辞める、教室を変える選択が必要な場合もあります。
親が子どもの話を聞くことで、親子の信頼関係も強くなります。
親の「こうした方が良い」という意見を押し付ける前に、まずは子どもがどうしたいかをじっくり聞いてあげましょう。
子どもが嫌がる理由の例
子どもの話を聞くことで「習い事」が嫌なのか、先生や友達が嫌なのかが見極められます。
いじめ
バレエ教室に通う小学2年生女の子。ある時期からレッスンを嫌がり、胃腸障害が出ていた。母親が理由を聞くとバレエ教室で特定の子からいじめられているとこと。先生に聞いても問題がないという返答。
後日、母親が発表会のバックステージでいじめの現場を目撃。すぐに先生に理由を伝えて辞めた。
胃腸障害はみるみる良くなり、辞めてから3カ月後には「違うバレエ教室でバレエを始めたい!」と言うようになった。
習い事自体が嫌
ピアノ教室に通う幼稚園(年中)の男の子。母親の希望でピアノを始めたが、すぐに辞めたがった。毎週出る宿題の曲も、母親に見張られて泣きながら練習。レッスンに行くのも嫌がっていた。
レッスン中も笑顔が少ないため、半年で辞めさせる。
その後、本人の希望で始めた体操教室には楽しそうに通っている。
教室(先生)と合わない集団学習塾に通う小学3年生の女の子。学力別にクラス分けされていない個人塾
だった。理解が早いため演習問題もすぐに終わってしまう。平易な宿題が大量に出るため、学習意欲が低下。
講師に相談するも、平易な課題が増えるのみ。3か月後、辞めて、学力でクラス分けされている大手塾に入った。入塾テストを受けて学力レベルに合ったクラスに入ったことで、学習意欲が戻ってきた。
幼児~小学校低学年の子が
嫌がる時の対処法
可能であれば一定期間、
保護者が習い事を見学する
先生に相談して可能であれば、レッスンや指導を見学させてもらいましょう。
小学校低学年までは、ママ・パパの側にいることで情緒が安定する子が多いです。
習い事に集中できるようになってくれば、親が付き添わなくても大丈夫になります。
習い事の後にお楽しみを入れる
習い事へ行く前にぐずる、面倒くさがるこの場合は、習い事の後に楽しみを作りましょう。
公園で遊ぶ、一緒におやつを作る、ガチャガチャをやらせてあげる、お迎えの時にちょっとしたおやつを持っていく・・・ちょっとした「お楽しみ」を準備しておくと、習い事に行く面倒さが薄れます。
習い事の成果
(できたこと、頑張ったこと)を褒める
サッカーや野球の試合で勝った、ピアノのコンクールで入賞した、水泳の進級テストで合格した、塾の全国模試で偏差値が上がった・・・などの特別な成果を上げた時は、多くの親御さんがお子さまを褒めることと思います。
ですが、目に見える成果がない場合、認めて褒めることを忘れがちではないでしょうか?
普段から習い事について、子どもから話を聞き出しましょう。
きっと「できるようになったこと、頑張ったこと」をママ・パパに教えてくれるはずです。
そこを大いに褒めてあげましょう。
幼児~小学校低学年の子のモチベーションを高めるのはママ・パパからの褒め言葉です。
自己肯定感と学習意欲が高まるので、習い事をもっと頑張りたくなるでしょう。
小学校高学年の子が
嫌がる時の対処法
習い事が自分に合っているかどうか、習い事を続けていくべきかどうかの判断は、子どもに任せよう。
高学年になると親が思っている以上に賢く、自己分析ができている子が多いです。
小学校低学年までと同様に、習い事を嫌がる理由を聞き出しても良いですが、お子さまによって話したがらないこともあります。
その場合は無理に聞き出さなくてもOKです。
子どもが習い事を辞めたい、教室を変えたい意思が強固であるならば休会する、辞めることを許可しましょう。
理由によっては辞める決断も必要!

習い事自体が楽しくない、先生と合わない、いじめ・・・子どもの心身に悪影響があると判断した場合は速やかに辞める、休会する決断をしましょう。
子どもを伸ばす習い事は「楽しく集中できる」ものです。
先生や他の生徒とのトラブルで精神状態が悪くなる習い事は続ける意味がありません。
人間関係で習い事が嫌になっている場合は、思い切って辞めて、違う教室に入り直すのも選択の一つです。
休会して様子を見る
習い事にやる気が出ない、何となく嫌になってしまった場合は、辞める前に一度「休会」してみましょう。
たいていの習い事が期限付きで休会を認めています。
ただ、「今日から、来週から」のように、直近のレッスンから休会するのは難しいです。
習い事の会則、利用規約で「休会希望の場合は、休会希望前月○日までに申し出る」のように決められています。
スムーズに行けば、申し出た翌月から休会することも可能です。
また休会中も月謝が発生する場合もあります。
何カ月も休会する場合は、休会中の月謝の有無を確認しましょう。
危険!逃げ癖、辞め癖をつける
「安易な辞め方」とは?

習い事をはじめて、すぐの「つまらない」「向いてないと思う」などのネガティブ発言を真に受けて、すぐに辞めさせてしまうと逃げ癖、辞め癖がついてしまうことがあります。
体操、バレエ、ダンス、学習塾、英会話、絵画・・・どんな習い事も慣れるまでは緊張もあるし、覚えることがたくさんあります。
数カ月は続けてみないと、向き不向き、その習い事の面白さはわからないものです。
子どもの心身に危険が及ぶような問題がない限り、半年間は続けましょう。
どんな習い事もはじめは、基礎練習の繰り返しや、基礎知識を学ぶことからスタートします。
「ストレッチがつらい」、「宿題に時間がかかる」、「画材の後片付けが面倒くさい」など、好きで始めた習い事にも、必ず「面倒・苦手なこと」があります。
これをこなし、乗り越えることで能力が向上し、習い事を楽しめるようになります。
子どものモチベーションを保つのは
親次第

先生に自分から質問する、家でも課題や練習に熱心に取り組む子もいる一方、「親に言われているから習っている感」が強く、受け身でやる気のない子もいます。
この学習意欲の差は子どもの性質によるものだけではありません。
親の関わり方が大きな影響を与えています。
子どもの習い事について関心を持ち、応援する気持を伝えるだけでモチベーションと学習意欲は育まれます。
ときどき習い事を見学する、習い事についての話を聞く、小さな進歩・変化をほめることで習い事に取り組む姿勢がきっと変わります。
他の子と比べない
わが子を応援するあまり、他の子と比べてやる気を出させようとするのは逆効果です。
子どもの自尊心を傷つけ、劣等感を感じさせるので、返ってやる気を削いでしまいます。
「○○ちゃんは後から入ったのに、もう〇級に進級したんだ。追い抜かされちゃったね。」
「次は○○君より良い点取らないとね。」
などと、他者と比較した発言で追い込むのは避けましょう。
子どもによって成長、上達の速度は違います。
その子の日々の頑張りを認めることが能力アップの近道になります。
大人の尺度で優劣をつけて、批判しないようにしましょう。
子供が習い事を嫌がったときの
体験談

次に子供が習い事を嫌がったときにした対応の「体験談」も確認しておきましょう。
上手くいった例、失敗した例を解説していきます。
上手くいった例
まずは上手くいった例から確認していきましょう。

子供が習い事を嫌がる時まず重要な事は「理由をしっかり聞く事」です。
なんで嫌なの?と聞き込んでいくとい意外と簡単な悩みであったり、先生と話し合うことで解決できる内容もあります。
我が家の場合は習い事先の同年代のこと少し喧嘩をしてしまったようで行きづらくなったみたいです。
そのことを先生に伝えたらうまく仲を取り持ってくれてまた「行きたい!」と言い出すようになりました。
(小学3年生保護者)

子供が1年ぐらいサッカー教室に通っていた時突然「行きたくない」と嫌がるようになりました。
理由を聞くとサッカーのコーチに厳しく指導され泣いてしまったことが原因のようでした。
一週だけお休みさせて話し合うことに。
その時効果的だったのは「サッカーをやりたい!」と言い出した時の想いを振り返ってみたことです。
「将来はサッカー選手になりたい!」と言っていたのでその時を思い出すように話してみました。
すると数日後「やっぱり行く」と自ら言い出したので良かったなと感じています。
(小学3年生保護者)

娘が1年ほど前から英会話教室に通っています。
最近、教室に行くの嫌がることが増えてきました。
その時効果的だったのは「目標設定」をし直したことです。
具体的には小学校のうちに「英検4級に合格する」というものです。
その設定をしてから「やる気スイッチ」が入り一気に楽しみながら取り組むようになりました!目標設定大事です!
(小学4年生保護者)
イライラしてしまった失敗談
次に失敗談を解説していきます。

子供が習い事に行くのを嫌がったときに、私もイライラしてしまい無理やり連れていきました。
別の仕事の予定もあったので休ませるわけには行かず…。
ただ、無理やり連れていっても余計嫌になるだけです。
大切なのはしっかり嫌がっている理由を聞いてあげることですよね。
ただ、時間がないとどうしても焦ってしまいます..

スイミングスクールに行く直前に「今日行きたくない」と言い出しました。
別の予定もあったので休ませるわけにはいかず「今日頑張ったら○○買ってあげる!」と物で釣ってしまいました。
その時はそれで乗り越えたのですが、次週も同じことに。
結局もので釣っても根本的な解決にはなりません。
しっかり話を聞いて一緒に解決していく姿勢が大切です。
習い事で「好き、得意」を見つけて
人生を豊かに

子どものうちに習い事を通して「好きなこと、得意なこと」をある程度、知っておくことで、進路選択の方向性がつけやすくなります。
将来どんな道に進んで、どうなりたいかがイメージできると、「何をすべきか」が見えてきます。
早いうちに将来像がある子ほど、具体的な目標設定がしやすく、勉強や準備も進めやすくなります。
習い事は子どもが興味を持ったものを、自由に習わせて成功体験・失敗体験をさせると良いでしょう。
親としては無難な「子どもが才能を発揮できそうな習い事」「頭が良くなりそうな習い事」を選んで欲しいですが、そうではない習い事でも「能力・脳力」は育ちます。
習い事の成功体験だけではなく、失敗・挫折した経験も、自分の特性を知る糧になります。
すぐに辞めてしまった習い事も、無駄ではないのです。
P.S
ここまで記事を読んでくださり、ありがとうございました。
最後までこの記事を読まれたということは、「あなたが本気でお子さんに向き合っている証拠」だと私は確信しています。
一般的に、ネットの記事は最後まで読む人は3割程度だと言われています。
つまり、悩んでいるフリをしながら結局は、本気じゃない、心の奥底では大した事だと思っていないという事です。
そんな中、あなたは最後まで記事を読まれたという事は、お子さんに真剣に向き合っている証拠です。
大変なことや、悩むことも多々あると思います。
ですが、真剣にお子さんに向き合っているあなたのお子さんであれば、きっと明るい未来が訪れると確信しています。
これからも、どうぞお子さんと真剣に向き合ってあげてください。